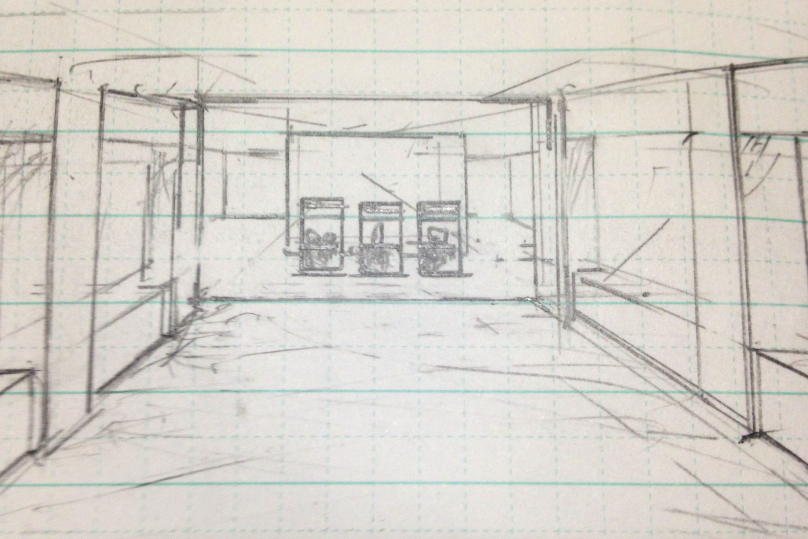特別展「第72回 正倉院展」見どころを押さえどこ

- ワンポイント情報☆彡
- 奈良国立博物館 最新情報 詳細⇒クリック
- 特別展「第72回 正倉院展」・奈良国立博物館
会期:2020/10/24(土)~11/9(月)・開催まとめ 詳細⇒クリック - 特別展「第72回 正倉院展」見どころを押さえどころ 詳細⇒クリック
- 期間限定・動画配信まとめ☆彡
11/30(月)迄・「第72回 正倉院展・研究員による宝物の解説Part1~Part5」 詳細⇒クリック - ▼一般発売(前売日時指定券)/ 発売開始 2020/9/26(土) 10:00~。
予定枚数終了しだい発売終了。
- ▼一般発売 / 予定枚数終了しだい発売終了。

開催履歴☆彡
- 2019年・特別展「第71回 正倉院展」関連・開催履歴☆彡
- ・[開催履歴・奈良博] 特別展 御即位記念「第71回 正倉院展」・奈良国立博物館
会期:2019/10/26(土)~11/14(木)・開催まとめ 詳細⇒クリック - ・[開催履歴] 正倉院学術シンポジウム2019「即位と正倉院宝物」2019/11/3(日・祝) 12:30開場 13:00~17:30 於:東大寺総合文化センター 金鐘ホール・参加費無料・申込先着順250名・申込期間10/7~10/28(月)必着・往復はがき又はウェブより 詳細⇒クリック
- ・[開催履歴] 「正倉院フォーラム2019」各会場別開催まとめ☆彡
大阪(9/23)、東京(9/29)、福岡(9/28)、名古屋(10/5) 詳細⇒クリック - ・[開催履歴・東博] 御即位記念特別展「正倉院の世界-皇室がまもり伝えた美-」・東京国立博物館
会期:2019/10/14(月)~11/24(日)・開催まとめ 詳細⇒クリック - ・特別展「第71回 正倉院展」見どころを押さえどころ 詳細⇒クリック
- 2018年・特別展「第70回 正倉院展」関連・開催履歴☆彡
- ・[開催履歴・奈良博] 特別展「第70回 正倉院展」開催履歴 詳細⇒クリック
- ・[開催履歴] 「正倉院フォーラム2018」開催まとめ 詳細⇒クリック
- 2017年・特別展「第69回 正倉院展」関連・開催履歴☆彡
- ・[開催履歴・奈良博] 特別展 「第69回 正倉院展」 開催履歴 詳細⇒クリック
- ・[開催履歴・奈良博]特別展 「第69回 正倉院展」見どころを押さえどこ 詳細⇒クリック
- ・[開催履歴] 「正倉院フォーラム2017」開催まとめ 詳細⇒クリック
特別展「第72回 正倉院展」見どころを押さえどこ
ここでは、奈良国立博物館で開催される特別展「第72回 正倉院展」(10月24日(土)~11月9日(月))の正倉院展の見どころ、押さえどこをまとめてみました。
期間限定(11/30迄)・動画配信
・「第72回 正倉院展・研究員による宝物の解説Part1~Part5」
動画配信・令和2年11月30日(月)までの期間限定で、「第72回 正倉院展・研究員による宝物の解説Part1~Part5」で配信がありました。
はじめに

今回は、新型コロナウイルス対策として当日券の販売はしていないので、事前に「前売日時指定券」の予約・発券が必要となります。さらに、入場制限として、1時間に入場者を約260人ということなので、例年と違い、事前に出陳品を確認して、観覧のポイントを絞り込んでおくことがよろしいようです。

当日券の販売が、ないのですね。前もって、観覧する日と時間を決めての予約・発券ですね。

正倉院の宝物は、東大寺大仏を造立した聖武天皇のご遺愛の品々を光明皇后が大仏に献納したことに始まります。のちに東大寺の儀式に使った法具も加わり、現在は、9,000点を数える宝物がある。なにがすごいかって言うと、この正倉院宝物は日本、中国(唐)や西域、ペルシャなどからの輸入品、それも古代の美術工芸の粋を集めた品々をはじめ、奈良時代の日本を知る史料としての正倉院文書や東大寺大仏開眼法要の品や古代の薬品なども所蔵されていて、貴重な文化財の宝庫、またシルクロードの東の終点ともいわれています。

9,000点の宝物の中で渡来品は 400点だけ。
素材は(ラピスラズリなどの素材は別)別。工芸品となっているもの。西アジア、ペルシャで作られたものは、ガラスの器だけなんだって。

ほんとに?ほとんどが渡来品かと思っていたよ。

正倉院は、校倉造りということしか知らなかったけど、私たちの知らない時代を過ごしてきた美術工芸品が時空を越えて見ることのできる。宝箱ですよね。
出陳される宝物総数と初出陳
今回は、楽器、伎楽面(ぎがくめん)、遊戯具(ゆうぎぐ)、調度品、佩飾品(はいしょくひん)、染織品、文書・経巻などが出陳され、正倉院宝物の主要なジャンルの名品が公開されるとのことです。
なかでも、武器・武具・馬具などが出陳され、古代の武人の装い、また、疫病との関わりを伝える品として、光明皇后が病人に分け与えるために東大寺に献納した薬物、「五色龍歯(ごしきりゅうし)」など8件が出陳されます。

令和2年の正倉院展に出陳される宝物総数は、59件(北倉17件、中倉23件、南倉16件、聖語蔵3件)で、このうちの4件は初出陳となります。
初出陳の内訳は、中倉より「続修正倉院古⽂書後集(ぞくしゅうしょうそういんこもんじょこうしゅう) 第⼗七巻」[更可請章疏等⽬録(さらにこうべきしょうしょとうもくろく)] 1巻、聖語蔵より「深密解脱経(じんみつげだつきょう)巻第三」唐経 1巻、「増壱阿含経(ぞういちあごんきょう)巻第⼗五」 光明皇后発願の写経1巻、「⼤⽅広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんきょう)巻第⼗⼆ ⼄」奈良時代の写経 1巻となっている。

えっ、聖語蔵って?

聖語蔵(しょうごぞう)って、正倉院の構内にある小いさな校倉造の倉庫のことだよ。その中には、正倉院文書とは別のもので仏教関係の経巻などが納められている。転害門のところにあった東大寺の尊勝院(そんしょういん)の経蔵が皇室に献納されて現在の場所にあるんだって。今回のこの聖語蔵からの初出陳は、3品あるね。

初めての公開される気になるのは、なあに?

初めての公開される気になるのが、「続修正倉院古文書後集 第十七巻」です。
この「続修正倉院古文書後集 第十七巻」は748年(天平20年)6月10日に僧の平摂(へいしょう)が、写経所で今後、書写すべきものとして選んだ書物のリストということです。どんなものがリストにあがっているか気になりますよね。
リストには、仏書をはじめ、史書、兵書、天文書とあります。この天文書は大いに気になるところです。

「続修正倉院古文書後集 第十七巻」は、仏書127部と、仏教以外の書物43部の書名と巻数が記されている。仏書は経典の注釈書や解説書が中心で、元暁(がんぎょう)など新羅(しらぎ)僧の著作を含むこと等から、新羅での滞在経験を持つ大安寺僧の審祥(しんしょう)の旧蔵書と推定されている。仏教以外の書物では、詩文集や史書、兵書、天文書、医書などがある。
たとえば『新修本草(しんしゅうほんぞう)』は、唐の高宗の顕慶4年(659)に完成した勅撰の本草学(ほんぞうがく)(医療に供する薬物の学問)の書物で、奈良時代前半にはわが国にもたらされており、このように写経所での書写も計画されていたことが知られる。

医書?

たとえば『新修本草(しんしゅうほんぞう)』は、唐の高宗の顕慶4年(659年)に完成した医療に供する薬物の学問、本草学(ほんぞうがく)の書物なんだよ。奈良時代前半にはわが国にもたらされていたんですね。
・ 開催され次第、新しい情報を追記していきます。乞、ご期待ですね。
・ 特別展「第72回 正倉院展」出陳品リスト(公式サイトへ) ⇒クリック
知っ得情報☆彡
- 特別展「第72回 正倉院展」出陳品
令和2年の正倉院展に出陳される宝物総数は、59件(北倉17件、中倉23件、南倉16件、聖語蔵3件)で、このうちの4件は初出陳となります。
初出陳の内訳は、中倉より「続修正倉院古⽂書後集(ぞくしゅうしょうそういんこもんじょこうしゅう) 第⼗七巻」[更可請章疏等⽬録(さらにこうべきしょうしょとうもくろく)] 1巻、聖語蔵より「深密解脱経(じんみつげだつきょう)巻第三」唐経 1巻、「増壱阿含経(ぞういちあごんきょう)巻第⼗五」 光明皇后発願の写経1巻、「⼤⽅広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんきょう)巻第⼗⼆ ⼄」奈良時代の写経 1巻となっている。 - 特別展「第71回 正倉院展」出陳品
令和元年は、41件(北倉14件、中倉8件、南倉17件、聖語蔵2件)、そのうち初出陳は、4件でした。
初出陳の内訳は、北倉より宝物の収納容器、古櫃(こき)が1合、南倉より鐘形の風鈴、金銅鎮鐸(こんどうのちんたく)が2口、聖語蔵より光明皇后御願経、四分律(しぶんりつ )巻第二十三 1巻となっている。
- 特別展「第71回 正倉院展」が閉幕
令和元年11月14日(木)に、全20日間の会期を終えて閉幕した。天皇陛下の即位を記念した「第71回 正倉院展」の入場者数は、昨年の247,832人を上回る277,133人。なんと15年連続20万人超えという結果だと報道されている。11月1日(金)には、通算入館者1,000万人目を祝う式典があり、東京都から初めての正倉院展という細川さんが記念すべき証明書を奈良国立博物館館長から授与された。「第1回正倉院展」は、昭和21年(1946年)10月に開催、22日間に約15万人という入館者だったというから、この通算入館者1,000万人をこえたと言うことは感動します。天平時代の時代より、多くの人に正倉院の宝物を護り語り継いで、そして昭和、令和と、未来へこれからも正倉院宝物の素晴らしさを伝えていきましょう。 - 特別展「第70回 正倉院展」入場者数:
平成30年11月12日(月)、17日間の会期を終えて閉幕した。平成最後の正倉院展の入場者数は、昨年の217,053人を上回る247,832人。なんと14年連続20万人超えという結果だと…。
参考☆彡
- 正倉院 ・宮内庁 ⇒ クリック
奈良・平安時代の重要物品を納める東大寺の正倉院。
正倉院宝物とその鑑賞を中心に紹介。『正倉院紀要』も掲載されている。 - 正倉院宝物検索・正倉院 ⇒ クリック
- e国宝 - 国立博物館所蔵 国宝・重要文化財 ⇒ クリック
- 第71回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第70回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第69回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第68回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第67回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第66回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 第65回正倉院展 出陳宝物一覧 ⇒ クリック
- 参考文献